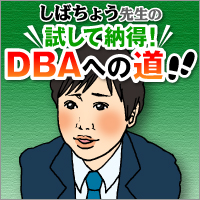はじめまして、こんにちは。この連載を担当する”しばちょう”こと柴田長(しばた つかさ)と申します。
日本オラクルのデータベース・スペシャリストとして、長年数多くのミッション・クリティカル案件への技術支援やお客様のシステムに最適なソリューション・デザインの提案、さらにはやパフォーマンス・トラブルの問題解決に従事してきました。数年間のマネジメントを経験ののち、現在はオラクルコーポレーションのデータベース開発部門の一員として、日本におけるExadataを中心としたデータベースの提案、及び、技術支援を担当しております。
これらの提案やトラブル解決を行う上で痛感していることは、SIer時代の開発現場やOracle GRID Centerでの実機検証の経験が確実に生かされているということです。経験しているからこそ、マニュアル棒読みの機能紹介では留まらず、瞬時にその機能の適用シナリオも含めて自信を持って自分の言葉(お客様に合わせた言葉)でお客様に提案できますし、早期にトラブル原因の当たりを付けたり解決のアイディアを閃いたりすることが可能になっていると思っています。
今回の連載は、正に体験して頂くことが主軸となります。単純な機能紹介ではなく手を動かして理解を深めて頂けるような連載にしていきたいと考えております。内容としては私が新人をDBAに育てる際に使用する課題をカスタマイズしたものであり、レベルとしては初級~中級、たまに上級を想定しております。これからDBAを目指される方、実機での作業から数年間離れられている方等々、多くの方にご活用頂ければ幸いです。

- 第59回 Active DatabaseからData Guard – Physical Standby Databaseの作成
- 第58回 RMANバックアップからData Guard – Physical Standby Databaseの作成
- 第57回 RMANバックアップから表領域を限定したデータベースの複製
- 第56回 [19c] Memoptimized Rowstore – Fast Ingest (高速収集)
- 番外編 Autonomous Database = 究極のOracle Database
- 第55回 SQLパフォーマンスの高速化の限界を目指せ!(3)
- 第54回 SQLパフォーマンスの高速化の限界を目指せ!(2)
- 第53回 SQLパフォーマンスの高速化の限界を目指せ!(1)
- 第52回 AWRを読むステップ4: 特定時間帯に発生する性能劣化の原因特定
- 第51回 AWRを読むステップ3: OLTPのスループット低下の原因特定
- 第50回 [12c R2] Oracle Database Cloud Service上にDB作成
- 第49回 [12c] ASMディスク・グループ内のディスクの置換
- 第48回 [12c] 時間隔(インターバル)パーティション表のクセ
- 第47回 [12c] オンライン・データファイルの移動
- 第46回 [12c] RMANバックアップからの表のリカバリ
- 第45回 Recovery ManagerのSWITCHコマンドでリストア時間ゼロ
- 第44回 Recovery ManagerのVALIDATEでリストア・リカバリに備える
- 第43回 SQL実行計画の共有とセッションのオプティマイザ関連パラメータ
- 第42回 [12c] 拡張索引圧縮(Advanced Index Compression)
- 第41回 [12c] オンラインでのパーティション移動
- 第40回 AWRを読むStep#2:アクセス数が多い表領域とセグメント
- 第39回 AWRを読むStep#1:バッファキャッシュ関連の待機イベントと統計情報
- 第38回 Flashback Drop機能による削除表の復旧と注意点
- 第37回 ORAchkを使用したデータベースのヘルス・チェック
- 第36回 SQLのパース処理とバインド変数の理解
- 第35回 ASMのミラーリングによるデータ保護(2) ~高速ミラー再同期
- 第34回 ASMのミラーリングによるデータ保護(1) ~障害グループと冗長性の回復
- 第33回 ASMのリバランスの動作
- 第32回 標準監査の基本的な使い方
- 第31回 ASMのストライピングとリバランスによるI/O性能の向上
- 第30回 ASMディスク・グループの作成と使用量の確認
- 第29回 UNDO表領域の管理~パフォーマンス・チューニング~
- 第28回 UNDO表領域の管理~保存期間の自動チューニング~
- 第27回 パーティション表の管理~ILMにおける表データの圧縮と索引の再構成
- 第26回 パーティション化による削除処理のパフォーマンス向上
- 第25回 パーティション化による問合せのパフォーマンス向上
- 第24回 Recovery ManagerによるData Recovery Advisorの活用
- 第23回 Recovery Managerにおけるバックアップ時間をResource Managerで制御
- 第22回 Recovery Managerによる高速差分増分バックアップ
- 第21回 Recovery Managerによる差分増分バックアップ
- 第20回 フラッシュバック・データベースのオーバーヘッド
- 第19回 フラッシュバック・データベースによる論理障害からの復旧
- 第18回 表のオンライン再定義でDML文の遅延を回避
- 第17回 表領域の縮小とセグメントの格納位置
- 第16回 OLTP表圧縮によるキャッシュ・ヒット率の向上
- 第15回 圧縮表への変更方法と注意点
- 第14回 基本圧縮の効果的な活用
- 第13回 行移行、行連鎖を理解し性能トラブルを未然に防ぐ(2)
- 第12回 行移行、行連鎖を理解し性能トラブルを未然に防ぐ(1)
- 第11回 オプティマイザ統計情報の管理 ~ヒストグラムの効果を体験してみる~
- 第10回 オプティマイザ統計情報の管理 ~保留中の統計情報を有効活用~
- 第9回 オプティマイザ統計情報の管理 ~統計収集の失効を制御してみる~
- 第8回 オプティマイザ統計情報の管理 ~統計収集の高速化を体験してみる~
- 第7回 表領域の管理方法を理解
- 第6回 続・SQLの実行計画からパフォーマンスの違いを読み解く
- 第5回 SQLの実行計画からパフォーマンスの違いを読み解く
- 第4回 続・データ領域管理の理解~ダイレクト・パス・インサート~
- 第3回 データ領域管理の理解~SQLチューニングにも挑戦~
- 第2回 表と表領域の関係
- 第1回 表領域の作成と拡張
【しばちょう先生の講演資料 & 動画ダウンロード】
【[Oracle Day] Developer Days 2024】
しばちょう先生が語る!Exadata Database Machineで実現するMAA主要テクノロジー [YouTube]
【Oracle Developer Days 2020】
Oracle Database := Converged Database [PDF]
データの価値を引き出すアプリ開発を実現するOracle Databaseの最新テクノロジー
【しばちょう先生が語る!オラクルデータベースの進化の歴史と最新技術動向】
【Oracle Database Connect 2018】
エキスパートはどう考えるか?体感!パフォーマンスチューニングⅡ(前半) [logmi]
エキスパートはどう考えるか?体感!パフォーマンスチューニングⅡ(後半) [logmi]
【Oracle Code Tokyo 2017】
【Oracle Database Connect 2017】
エキスパートはどう考えるか?体感!パフォーマンスチューニング [YouTube]
【Oracle DBA & Developer Day 2016】
ストレージ管理のベスト・プラクティス ~ASMからExadataまで~ [PDF]
【Oracle Database Connect 2016】
DB障害解決の極意 実体験に基づくトラブル対応と対策案 [PDF]
【Oracle Cloud Days Tokyo 2015】
Oracle Database 12c最新情報 ~MAA Best Practice~ [PDF]
【Oracle DBA & Developer Day 2014】
しばちょう先生による特別講義! RMANの運用と高速化チューニング [PDF]
【Oracle DBA & Developer Day 2013】
高可用性ベスト・プラクティスによるデータ破壊対策完全版 [PDF]
【Oracle DBA & Developer Day 2012】
高可用性システムに適した管理性と性能を向上させる ASMとRMANの魅力 [PDF]
【Oracle DBA & Developer Day 2011】
どこまでチューニングできるのか?最新Oracle Database 高速化手法 [PDF]
どこまでチューニングできるのか?最新Oracle Database 高速化手法 [PDF]
Authors