※本記事は、Piers Conwayによる“Digital-first customer service: Creating the convenience customers crave”を翻訳したものです。
今日、顧客にとって、カスタマーサービスとの接点は、かつてなく重要になっています。
コロナ禍により、対面でのカスタマーサービスが減少し、顧客が従来のコールセンターといったチャネルに頼らざるを得なくなった結果、セルフサービスによる、便利なデジタル体験が求められるようになりました。
多くの顧客にとって、利便性こそが最も関心を寄せることです。NICE inContactの調査によると、アメリカ人の65%以上が、オンラインでのブランド体験を望んでいると言われています。
「オンライン」は、今日において幅広い意味を持つ言葉になっており、顧客にとっても馴染みのあるものです。その意味は、人によって、ソーシャルメディアのことを指したり、企業のウェブサイトやモバイルアプリにおけるセルフサービスの体験を指したりすることもあります。
「オンライン」の意味がどんなものであっても、顧客が求めているのは、早くて、簡単で、より便利なものであることには間違いないでしょう。担当者からたらい回しにされ、同じことを何度も説明したり、チャット担当者に問い合わせるために、長い時間パソコンの前で順番を待っていたりすることは、望んでいません。しかしながら、未だに多くのカスタマーサービスの体験が、このような状況のままです。
全4回の連載”カスタマーサービスはデジタルファーストであれ”の最終回である本記事では、ハイパーコンビニエント(お客様にとって便利)であることの位置付けを、顧客とカスタマーサービス担当双方の視点から説明し、この考え方によって、あなたの企業が、競合他社からどのように差別化されるのか記載します。
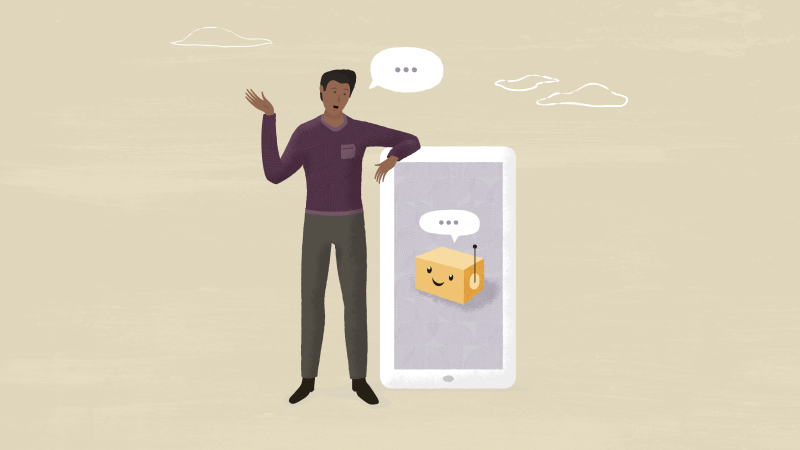
ハイパーコンビニエントなサービスとは?
顧客にとっての利便性は、必ずしも企業にとっての利便性であるとは限りません。ハイパーコンビニエントなサービスは、企業側の効率化を目的としてプロセスを設計することではなく、お客様視点での利便性を追求することです。
ハイパーコンビニエントなサービスにおいては、自動化が鍵となります。NICE inContactの調査によると、顧客の84%が、企業とのやり取りを、セルフサービスで行いたいと考えています。注文状況の確認、個人情報の変更、予約の変更といったセルフサービスのツールを用意することは、便利なカスタマーサービスを提供する一つの方法であり、顧客にとってのフリクションを減らすための自動化に繋がります。
デジタルコンシェルジュのようなチャットボットも、人気を博しつつあります。一般的な質問に回答するだけでない、賢さを持つようになってきています。
こうしたチャットボットは、カスタマーサービスの自動化に役立つでしょう。注文やアセットを管理するバックオフィスのシステムと連携し、利便性の高いサービスメニューを表示したり、大量の顧客データにアクセスし、顧客のニーズを理解することで、プロアクティブな対応や、同じ説明を何度もするような状況(64%の顧客が、チャットボットから人間の担当者に切り替える際に経験していると言われています)を避けたりすることができるようになります。
こうしたテクノロジーにより、顧客体験を改善するだけでなく、人間の担当者への問い合わせの削減にも繋がります。また、人間の担当者が必要な場面であっても、データが事前に自動で集まっているので、状況に応じた提案ができるようになります。人間の担当者は、価値のある顧客情報にアクセスできるため、より少ない質問で、効率的に顧客の抱える問題を解消することができます。
多様なチャネルと一貫性こそが成功の要因
顧客は、チャットボットから人間の担当者へのスムーズな切り替えを期待しています。NICE inContactの調査によると、94%の顧客が、セルフサービスのツールを使用している際、カスタマーサービス担当者にシームレスに繋がりたいと考えており、83%の顧客が、チャットボットを使用している際、人間とのチャット・メール・電話に切り替えたいと考えています。
これを実現するには、顧客が望むチャネルを用意することが必要です。SMSやソーシャルメディア等の複数チャネルでやり取りできるメッセージングツールを使うと良いでしょう。
さらに、複数のチャネルを用意するだけではなく、一貫性を持つことが重要です。PCからチャットのやり取りをしており、とある事情で中断することになったお客様を想像してみてください。その後の会話が、SMSといった非同期型の方法で、シームレスに継続できることが、理想と言えるでしょう。顧客とカスタマーサービス担当者が、柔軟性を持ったやり取りができるようにすることが求められます。
ハイパーコンビニエントなサービスが、隠れた組織のサイロを明らかにする
企業にとっては、営業、サービス、経理などの組織ごとに、プロセスを自動化し、運用する方が楽な場合も多いでしょう。組織ごとに、異なるルール、権限、テクノロジー、メソドロジー、文化、データベース、法規制、コストセンター、ポリシーが存在しているはずです。そこでのプロセスは、単一の組織とツールにのみ影響しているだけです。
個別最適で組織を運営することは、企業にとっては合理的かもしれませんが、顧客にとってはそうではありません。顧客からは、組織の境界やサイロは見えませんし、見ようともしません。顧客は、シンプルに企業ブランドとやり取りをしているのです。カスタマーサービスが、複数の組織にまたがり、データのサイロとともに、複雑なプロセスとなっているのであれば、自動化は難しくなります。言うまでもなく、カスタマーサービス体験も、その影響を受けます。
ハイパーコンビニエントなサービスを提供することは、顧客中心の考え方を軸としています。顧客の視点から体験を慎重に考えることで、分断されたり、フリクションやイライラを感じたりするプロセスを明らかにすることができるはずです。それらを改善することで、自動化を行いながら、顧客から組織の複雑性を隠すことができるようになります。
ワンクリックでの注文や返品、様々な部門から5分で必要な書類が集まるやり取り、テキストや画像を送信するだけで済む苦情の報告…等が、ハイパーコンビニエントなサービスの例です。
ハイパーコンビニエントなサービスは、長期視点で計画された戦略であり、企業側のロジックではなく、顧客側の視点で実現するものです。顧客がすぐに問題を解決できるようなサービス体験を実現するために、自動化や、多様なチャネルでの一貫性に対して、投資することが求められます。
Oracleのサービス体験に関する最新の考え方については、この連載”カスタマーサービスはデジタルファーストであれ”の以下の関連記事をご覧ください。