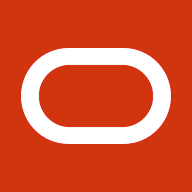本記事はMitch Wagnerによる“Fugaku, the world’s fastest supercomputer, steers toward ‘Society 5.0’” を翻訳したものです。
関連記事:「理化学研究所、Oracle Cloudで「富岳」の高度な計算資源の有効活用と研究成果創出を促進」
著者:Mitch Wagner
2021年11月16日
理化学研究所と富士通株式会社が共同開発したスパーコンピュータ「富岳」は、世界のスーパーコンピュータの性能ランキングである第58回「TOP500」リストで、4期連続の世界第1位を獲得しました。世界最速のスーパーコンピュータ「富岳」を開発したチームは、この勝利を、デジタル技術の助けを借りて世界の大きな社会的課題を解決する「Society 5.0」実現に向けた一歩と捉えています。
「富岳」を開発した理化学研究所計算科学研究センター(神戸市)の松岡聡センター長は、「私たちは社会を変革し、気候、長寿、経済格差、カーボンニュートラルな社会の実現など、持続可能性に関するすべての困難な問題を解決するために、本質的にはこれらの分野におけるデジタル・トランスフォーメーションを進めるために、豊富な情報技術を用います。」と述べています。
第5期科学技術基本計画において、Society 5.0は「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」と定義されています。
Society 5.0を実現するためには、スーパーコンピュータが象牙の塔から出てくる必要がありました。これまでスーパーコンピュータは、接続性が限られた特殊な環境でした。しかし今では、理研は「富岳」によって、スーパーコンピュータをさまざまな用途に利用できるようになりました。
そして、Society 5.0のビジョンを完全に達成するために、スーパーコンピュータをパブリック・クラウドと連携させることにしたのです。

理化学研究所計算科学研究センター 松岡聡センター長
松岡聡センター長は、オラクルのCLoud Engineering Senior Director Taylor Newillとの対談インタビュー動画の中で 「我々は、スーパーコンピュータが昔のように数字を計算するだけの孤立したものではなく、インフラに不可欠なものとなり、容量と性能が向上すると信じています。」と語っています。
国の誇り
6月に開催された世界最速のスーパーコンピューターを決めるTOP500において、「富岳」は米国や中国を抑え、3回連続でトップに立ちました。理研と富士通が共同開発した「富岳」は、HPLベンチマークで442Pflop/sを達成し、2位のIBM社製スーパーコンピュータ「Summit」に3倍の差をつけました。
一度ならず三度までも栄冠を手にしたことは、国の誇りであると松岡氏は言います。「困難な時代にあって、日本国民の士気を高めることができました」と。富岳は、日本を代表する山である富士山の別名です。
富岳は、従来の機械よりも性能が高いだけでなく、マシンとして根本的に違います。これまでの日本のマシンは、特殊でした。例えば、2002年に稼働した「地球シミュレータ」は、気候科学に特化したものでした。しかし、「富岳」は、2012年に完成した理研の「京」と同様に汎用的な目的のためのマシンです。
富岳の設計にあたっては、エネルギー、気候、医学・薬学、製造、基礎科学など、持続可能な社会の実現に向けて活動する主要なステークホルダーからの要望を取り入れました。富岳は、9つのフォーカスエリアのそれぞれで1つのアプリケーションを実行するように最適化されています。富岳は稼働して間もないですが、COVID-19、量子物理学、津波の浸水予測など、すでにさまざまな分野の研究に活用されています。
「富岳の目的は、単に性能を大幅に向上させるだけでなく、あたかも大きなX86クラスタを構築するかのように、最大限の汎用性を持たせることでした」と松岡氏は語ります。
そのために富岳では、富士通のARM A64FX-158,976を中心としたARMプロセッサを432ラック搭載しています。
これはスマートフォンに使われているようなコモディティなプロセッサーではありません。富岳では、1ワットあたり、1チップあたり、1円あたりで最大の性能を発揮できるように、必要なエネルギーと経済的コストを最小限に抑えた専用のプロセッサーを使用しています。それにより、富岳は、先代の「京」の40倍の速度を持ちながら、2倍の電力しか消費しません。
Take a tour of the supercomputer Fugaku – YouTube
パブリック・クラウドとの連携
富岳は、Oracle Cloud Infrastructureを弾力的なハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)用のストレージとして利用し、大学や研究機関が日本の学術情報ネットワーク(SINET)を介して安全かつ低コストで接続できるようにしています。また、専用のプライベート・ネットワーク接続であるOracle Cloud Infrastructure FastConnectも利用しています。
富岳のクラウド利用はまだ少ないですが、今後、スパコンをユビキタスにするためには、クラウドが不可欠だと松岡氏は言います。スーパーコンピュータは、ストレージやデータベースなどのツールと並んで、クラウドのリソースのひとつになるでしょう。
オラクルのような商用クラウドサービスは、スーパーコンピュータを補完するものになるでしょう。 「商用クラウド事業者は、ストレージや一般的なデータサービスの提供など、非常に優れたサービスを提供しています。一方で、『富岳』のような大容量でシミュレーションもできるスーパーコンピュータには、商用クラウドではできないことがあります」と松岡氏は言います。「それらはすべて統合されるべきです。」
例えば、「富岳」は、工場、飛行機、都市、気候・気象システムなどの実世界の物体をリアルタイムにデジタルシミュレーションする「デジタルツイン」アプリケーションを実現するためのデータ処理用シミュレーション機能を提供しています。デジタルツインでは、毎秒1テラバイトのデータを生成するセンサーからデータを収集する必要があり、高性能・大容量のストレージが必要となります。
理化学研究所が富岳にオラクルクラウドを採用した理由は、コンピュートおよびストレージ・リソースを低コスト、安全かつ高速に利用可能にするオラクルのストレージとデータに関する知見と経験です。オラクルは、富岳に不足している長期保存機能を、富岳と同じAPIを使って利用者に提供し、富岳とOracle Cloud Infrastructure間の自動化を実現します。「ストレージ層の統合は非常にスムーズに行いたいと思っていました。」と松岡氏は語ります。
富岳のストレージ容量は現在150ペタバイトと巨大ですが、潜在能力を考えるとまだまだ小さいと言えます。しかし、富岳は正式に稼働してからまだ5カ月しか経っていません。研究者がプロジェクトを完了し、割り当てを終えた後は、データを長期保存する必要があります。「このようなデータの一部は、Oracle Cloudに移行することが予想されます。なぜなら、Oracle Cloudはデータを置くのに最も簡単な場所だからです。多くの人にとって、他に適した場所はありません」と松岡氏は言います。
未来に向けて
今のところ、富岳のユーザーは大学関係者ですが、松岡氏は将来的には産業界での採用も視野に入れており、目に見える成果を求めています。産業界のユーザーは、「富岳」を補完するために、商用のクラウドHPCを必要とするでしょう。
たとえば「富岳」に適さない産業アプリケーションもあるでしょう。その場合はユーザー側が、社会的に有益なアプリケーションであると認められる必要があります。もし「富岳」に適さないと判断されたら、商用HPCに移行します。
同様に、「富岳」ではユーザーが自分の仕事について情報を開示する必要があるため、機密性を必要とするビジネスでは、ワークロードを商用クラウドに移すことになるでしょう。「富岳」とクラウドHPCは、データやアプリケーションを簡単に移動させるために、同じAPIを使用する必要があります。「将来的には、このインフラがクラウドの中でどんどんユビキタスになっていくと考えています」と松岡は言います。「これは、クラウドベンダーがすぐに採用する技術です」。
富岳の開発チームは、いまもたゆまず進んでいます。
「私たちの情熱は、次世代の富岳を設計・構築することです。コンピュータでもレーシングカーでも、技術を開発するときは、本質的に良いものを目指さなければならないのです。」と松岡氏は言っています。