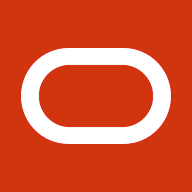日本オラクル株式会社が参画するGreen x Digital コンソーシアムによるサプライチェーンCO2排出量見える化に向けた、仮想サプライチェーン上でのCO2排出量データ連携の実証実験に成功したことをお知らせします。
一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が事務局を務める Green x Digital コンソーシアムは、サプライチェーンCO2データ*1見える化の実現に向け、仮想サプライチェーン上でCO2データ連携を行う実証実験に成功したことを発表しました(発表資料はこちら)。本実証実験は、グローバルかつ業界横断でCO2データ交換を実現することを視野に入れた、日本で初めての試みです。本実証実験の成功は、同コンソーシアムが策定したCO2データ算定方法と技術仕様の社会実装を後押しし、サプライチェーンCO2データ見える化の実現に貢献します。
*1) IPCCが定める温室効果ガス排出量(GHG排出量)のCO2等価量(kg-CO2 e等と表記される)を指します。二酸化炭素以外の温室効果ガスを含みます。
日本オラクルは、これまでもGreen x Digital コンソーシアムに正会員として参加しており、今回の実証実験にも協力しています。本実証実験では、株式会社野村総合研究所が2023年中にサービス開始を予定しているCO2排出量算定・データ連携ソリューションであるNRI-CTSの一部として、Oracle Databaseの機能であるブロックチェーン表が利用されました。
Green x Digital コンソーシアムの見える化ワーキンググループでは、デジタル技術を活用し、サプライチェーンの企業間でCO2排出量データを連携しスコープ3を含む見える化のための仕組みを検討、「CO2可視化フレームワーク」と「データ連携のための技術仕様」を策定しました。実証実験の中で得られた知見をもとに、グローバルレベルでの相互運用性を確保しつつ、より多くの企業にとって利用しやすい先進的な取り組みとして、「CO2可視化フレームワーク」と「データ連携のための技術仕様」のアップデートを進めます。
2022年9月~2023年1月にかけて行われた実証実験「フェーズ1」では、異なるソリューション間でのCO2排出量データ連携の実証が行われました。続いて実施された今回の実証実験「フェーズ2」では、日本オラクルを含むソリューション提供企業、およびソリューションのユーザー企業、合わせて32社が参加しました。
「フェーズ2」では、サプライチェーン上の複数企業群が異なるCO2データ見える化ソリューションを使用した場合でも、「共通の方法」と「フォーマット」という共通言語を用いてCO2データを算定しました。これにより、複数のソリューションが連携することでサプライチェーンの上流から下流までCO2データを受け渡すことが可能であることを実証しました。今回使用した「CO2可視化フレームワーク」および「データ連携のための技術仕様」が普及することで、ユーザー企業においてはソリューション導入時の選択の幅が広がります。また、ソリューションを提供する企業においても他社との個別調整が不要となり開発が効率化できるため、サプライチェーンCO2排出量データの見える化の早期実現に繋がることが期待されます。技術実証「フェーズ2」成功の発表の詳細については、こちらを参照ください。
日本オラクルはこれまでも、デジタル技術を活用した社会課題解決や産官学連携によるスマートシティ実現に向けた活動を推進しています。今回の実証実験の参画を通じて、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、より一層、取り組んでいきます。