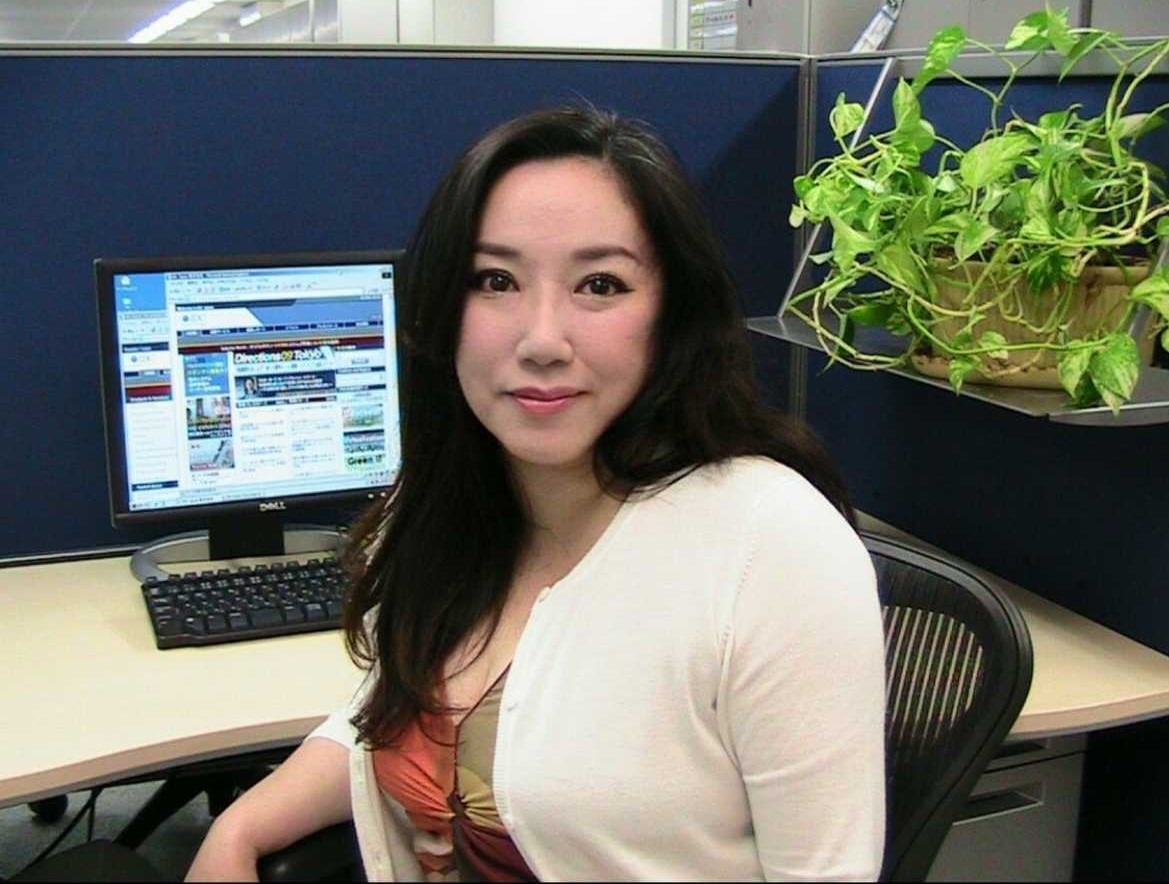本記事は2025年3月19日にビジネスフォーラム社主催のウェビナー「公共DXサミット2025 「2025年の崖」を超えて広がる未来へ ~公共機関・大学が直面する課題とデジタルイノベーションが描く解決の道筋~」において、基調講演にて登壇された株式会社AIST Solutions Vice CTO(デジタル庁 シニアエキスパート)博士(工学)(元:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室長)和泉 憲明氏が、セミナーの最後にノンフィクションライターの酒井真弓氏のインタビューで、大学・公共機関のDXについて総括された内容を元にご紹介するものです。
ウェビナー全体のアジェンダについては以下のURLよりご確認ください。
(本ウェビナーは既に終了しておりますがアジェンダ等のご確認は可能です)
https://www.b-forum.net/event/jp1942jcai/
DX(デジタルトランスフォーメーション)が、大学や公共機関にも急速に浸透しつつある昨今。
しかし「どこから始めるべきか?」「現場はついていけるのか?」といった疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
今回の対談では、静岡大学情報学部助手からキャリアをスタートし、経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室長時代には、官民連携のグローバルで勝てるDXをリードされた和泉氏ご自身の経験や実感をもとに、大学・公共分野のDXの核心を語って頂きました。
DXは“ネガティブな苦行”ではない。目的は「強くなること」
和泉氏は冒頭、「DXは辛さを乗り越えて得られる喜びがあるから取り組むもの」と語ります。
「デジタルって、正解のないゴールですよね。でも、ゴールを描ければ、そこに向かうプロセスが前向きなものになる。地獄に落ちないためじゃなく、強くなるためにやるんです。」
大学や公共機関が置かれている状況は厳しく、教員の業務も多岐に渡っています。しかし、そこで生まれる学生や仲間との“つながり”こそが、現場を支える力であり、DXの先にもポジティブな未来があると示唆しています。
最初にやるべきは「自分たちの勝ち方」を定めること
「デジタル投資の前に必要なのは、自分たちが何を目指すのかを明確にすること」
和泉氏は、これを“相場感”と表現します。
「ITやERPを入れる前に、“どこへ向かうのか”という目的地を組織全体で共有する必要があります。」
たとえば、大学であれば「就職率100%を目指す」「研究力を強化する」など、組織ごとに異なるゴールがあります。それを定めずにツール導入から入ると、目的と手段がかみ合わず、現場が疲弊するだけです。
スモールスタートの“罠”に注意を
よく言われる「まずは小さく始める」という考え方にも、和泉氏は一石を投じます。
「小さく始めるのが悪いのではなく、本質を小さく切り出せていないのが問題です。」
例え話として登場したのは、“包丁と料理”。包丁(=ツール)を買っても、自分がどんな料理を作りたいのかが不明確なら、結局うまく使えない。それと同じで、DXも目的に即した設計が重要なのです。
業務改革(BPR)は、現場の“納得感”から始まる
大学や研究機関では、教員や研究者が多くの業務を兼務している現実があります。そこへさらに申請・決裁などの業務が増えれば、効率はむしろ悪化します。
「悪平等になってはいけない。すべてを現場任せにするのではなく、組織として効率的なビジネスプロセスを設計する必要があります。」
和泉氏は、「学生満足」や「研究成果」といった“大学ごとの“勝ち方”に応じた業務再設計(BPR)が必要だと強調します。
ITは道具。使いこなすのは“現場”
システムベンダーにすべてを委ねるのではなく、現場が「自分たちの業務に合う道具」を選び取る目線が重要です。
「包丁屋さんに、“どんな料理を作ればいいですか?”って聞いても仕方ないですよね?」
つまり、道具の話ではなく、「どう強くなるか」「どこに向かうか」を現場が主体的に考えることこそが、DX成功の鍵なのです。
最後に:DXは“正しさ”ではなく“楽しさ”で進めるもの
対談の最後に、和泉氏はこう締めくくります。
「デジタルはITの延長ではない。まだ先行事例の少ないこの時代に、“勝ち方”を見つけて突き抜ける大学や組織が出てきたら、そこから未来が動き出す。だからDXはネガティブなものではなく、ポジティブにとらえてほしい。」
本ブログをご拝読頂いた和泉氏から補足コメントを頂きましたので、こちらに編集後記として追記させて頂きます。
デジタル変革というある種の混乱期に、いかにライバルに勝ち抜くか、というゲームであると考えれば、そのゲームを通して勝ち抜く楽しさとして実感できるのではないか?(「そういう勝負に勝つ楽しみ」とすべき)、ということかと思います。なので、相場観の下、勝ち抜くイメージを持ちながら、「ランナーを塁に進めた」「得点を入れた」「ゲームに勝った」というプロセスとして実感出来れば、むしろ、DXというゲームに参加したい(あるいは、そのゲームを単に観戦するのではなく応援したい)となるのでは、と思います。
まとめ:大学・公共機関DXの成功ポイント
1.まず“目的地”を明確にする(相場感の共有)
2.目的に合った業務改革(BPR)を設計する
3.ツールは“目的達成の手段”として選ぶ
4.現場と経営が一体となってビジョンを描く
5.ポジティブに、楽しみながら取り組む
DXは「苦しみの先にある未来」ではなく、「今よりもっとワクワクする社会を創るための一歩」とする和泉氏の言葉は、公共・大学に拠らず、民間企業の組織においても本質的な示唆なのではないでしょうか?
本セミナーの企画から開催までをサポートさせて頂いた筆者としても、今、改めて和泉氏が語られた内容をこうして記事にしながら、「DXの本来の目的とは何か?」について考えた時、今ある業務プロセスをデジタル化して便利になることは大切ですが、そこがゴールなのではなく、それによって得られる時間やコスト、人的なリソースを、ワクワクする会社や組織作りへ活かしていく、DXの最終的なゴールはワークフォースエンゲージメントであるのかも、と思った次第です。
オラクルでは、お客様がより適切な意思決定を迅速に行い、従業員の効率性を向上させるために、ビジネスに特化したAIを構築しています。Oracle Fusion Cloud Applicationsに組み込まれた従来のAIと生成AIにより、お客様は、ビジネスを強化するために日々使用しているソフトウェア環境を離れることなく、必要なときに必要な場所でAIによる回答を得ることができます。
以下のサイトより、Oracle AI for Fusion Applicationsの動画やコンテンツをご確認頂く事が出来ます。ご興味のある方はDXのゴールに向けて是非、AIが組み込まれたOracle Cloud Applications AI機能による未来に向けたバリューをご確認下さい。
https://www.oracle.com/jp/applications/fusion-ai/