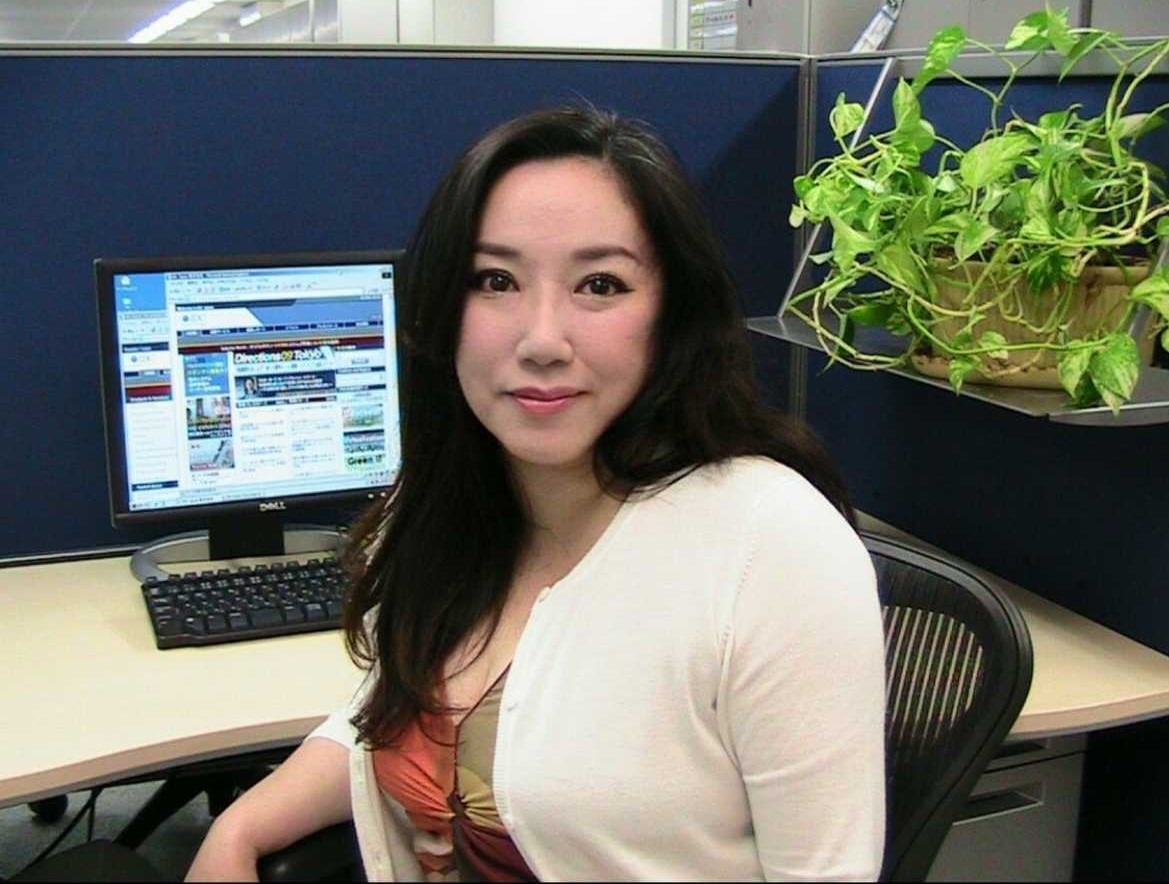2025年3月25日に開催されたオラクル開催のウェビナー「非財務情報 × 財務戦略:企業価値向上のための新たな一手 ~最新の非財務情報開示と戦略的活用で未来の成長を加速させる~」では、アットストリームコンサルティング様より企業価値を高めるうえで重要性が増す「非財務情報の戦略的活用」について、制度トレンドから具体的な経営管理への落とし込み方まで、非常に実践的な視点が共有されました。
オラクルからは「Oracle Cloud EPMで実現する「財務×非財務」統合管理とESG報告の未来」として、Oracle Cloud EPMのEPM for Sustainabilityソリューションの概要と、EPMで実現する「財務×非財務」の実現イメージ、インサイト機能による異常値検知などの活用イメージをご紹介しました。
本ブログ記事では、その内容を踏まえ、非財務情報を財務戦略とつなぐ「戦略的開示」の実践ステップをご紹介します。
1.なぜ今「財務✕非財務」なのか?
日本企業のPBRはなぜ低いのか?
プライム企業の平均PBRが1.2倍程度にとどまる日本企業は、欧米企業(例:米国平均3倍)に比べて評価が伸び悩んでいます。その背景には、バランスシートに乗らない「見えざる価値」=非財務資産が市場に十分伝わっていないという課題があります。
企業価値とは、「財務的価値」と「見えざる価値(非財務)」の両輪で構成される。
その「見えざる価値」を正しく開示し、ステークホルダーに伝えることが求められているのです。
2.非財務情報開示の潮流と企業への影響
グローバルで加速する規制の強化
・EU CSRD(企業サステナビリティ報告指令):2025年よりEU子会社を有する日本企業も対象
・ESRS(開示基準):環境・社会・ガバナンスの詳細項目と第三者保証の義務化
・ダブルマテリアリティ:企業→社会/社会→企業の両視点でのマテリアリティ設定が必須に
TCFDに比べ、CSRD/ESRSは「数値」や「結果」に踏み込んだ開示が求められ、プロセスと成果の両面での説明責任が強まっています。
3.戦略的開示の実践ステップ
ー非財務を「やらされ感」で終わらせないためにー
▼ レベルごとに整理された開示成熟度
- レベル1:未着手〜開示義務への初動対応フェーズ
- レベル2:形式的な開示の定着フェーズ
- レベル3:戦略と非財務情報の統合フェーズ
- レベル4:戦略的開示の実践フェーズ
一足飛びにレベル4を達成しようとせず、戦略的開示を見据えた自社の対応状況をまずは把握する必要があります。多くの企業においては、レベル3の到達に困難を感じている印象を持っています。たとえば、「残業時間削減(ESG目標)」と「売上拡大(経営目標)」が矛盾しているようでは、両者の統合は成り立ちません。戦略的開示には、トレードオフ構造の可視化と調整が不可欠です。
4.財務に効く非財務指標とは?
ー部門別・事業別に見る「ESGの手応え」ー
すべての非財務KPIが等しく価値を生むわけではありません。重要なのは、「財務との相関」を把握し、重点施策を見極めることです。あらゆる非財務情報の開示が求められており、その対応に追われている現状があるかもしれません。その中においても、自社の目指すべき姿や事業の特性、成長フェーズによってKPIは一様ではないことを理解しつつ、本当に管理すべき、財務成果に寄与する指標を設定する必要があります。
▼ 事例:2つの事業における非財務指標の違い
上記に関連してですが、事業によってKPIは異なります。一つの手法として、財務数値の推移の相関を見ながら、財務に効く非財務のKPIを特定することができます。
- 事業A:人的資本が利益率に影響→戦略的KPIとして離職率低減や従業員満足度向上、投資対象としては人事制度やエンゲージメント施策、職場環境改善など
- 事業B:環境コストが利益率に影響→戦略的KPIとしてはCO₂排出量の削減、廃棄物処理コストの最適化、投資対象としては省エネ設備、再エネ活用、サプライチェーン最適化など
マテリアリティが「CO₂排出」だからといって、全社一律に進めるのではなく、事業ごとの収益貢献性に基づく選択と集中がカギになります。
5.実行基盤を支えるOracle Cloud EPMの活用
OracleのEPM for Sustainabilityを活用することで、以下が可能になります。
- 財務・非財務データの一元管理
- CSRD/TCFD/GRI等へのマルチ対応
- 目標と実績のPDCA管理
- 財務指標との相関分析(利益率・PBRとの関連性)
- ナラティブレポート機能によるレビュー支援
- AIによる異常値検知と予測
特に、「計画」と「実績」を一体で管理できる点は、形式的な開示から本質的な経営管理ツールへと変貌させる大きな武器になります。
※EPM for Sustainabilityについては、日本オラクル技術メンバーが解説するオンデマンド・ウェビナーの中から「Oracle EPM Cloud- EPM for Sustainabilityのご紹介」をご確認ください。
6.戦略的開示とは、“なぜ”を語れること
最後に強調されたのは、「なぜ、その非財務KPIを重視しているのか」という内発的な動機の明確化でした。開示項目の優先順位は、ステークホルダーと対話しながら、「自社の価値創造とどう結びついているか」を示せることが求められます。
まとめ 非財務情報の開示=ゴールはなく「経営の道具」に
- 見えざる価値の正確な開示は、企業のPBR向上への第一歩
- 重要なのは、「財務に効く非財務指標」を見極める視点
- 戦略とデータ、システムを一体化し、説明可能な経営を目指す
企業の競争力は財務と非財務情報の戦略的開示の巧拙に表れます。単なる規制や義務対応の延長としての報告ではなく、「どの指標が経営や財務に貢献するのか」を捉え、意思決定に生かしていくことで、非財務情報を本質的な企業力の強化ツールとして活用をご検討される一助となれば幸いです。