高い技術力でプロジェクトを成功へ導くカギ
~日立製作所のエンジニアの取り組みとは~
こんにちは。OPN事務局です。今回は、株式会社 日立製作所様から、「2024 Oracle Partner Awards」のグローバルで最も優れたパートナーを表彰する「Regional Best in Class Award in Customer Success」受賞の対象となった事例を担当されたエンジニア、片山 仁史様、三澤 匠様、野中 一鴻様のお三方にスポットライトを当てご紹介します。
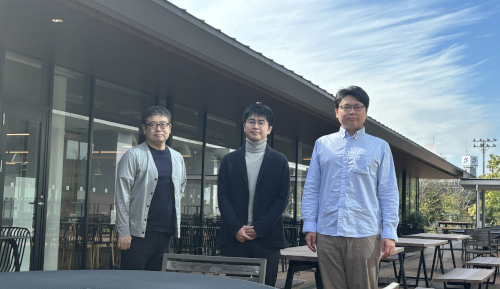
マネージド&プラットフォームサービス事業部
ミドルウェア本部
データベースサービス部
片山 仁史 様
マネージド&プラットフォームサービス事業部
ミドルウェア本部
データベースサービス部
三澤 匠 様
マネージド&プラットフォームサービス事業部
ミドルウェア本部
データベースサービス部
野中 一鴻 様
▼現在のお仕事についてお聞かせください。
片山様:
入社20年目になります。ずっと Oracle製品を担当しておりまして、サポートサービスの担当を経て現在はOracle製品の活用相談、Oracle データベース、OCIの技術支援をしています。
三澤様:
入社9年目になります。同じくOracle製品を担当しており、Oracle データベースと OCIに関するサービス開発やお客さま向けの技術支援、拡販活動を担当しています。
野中様:
入社7年目になります。入社してからずっとOracle データベースとOCIのソリューション開発/お客さまの現場での技術支援などを行っております。
▼御社の2019年からのOCIに対する取り組みについて教えてください。
野中様:
2019年からパブリッククラウドサービスであるOCIがリリースされ、弊部でも2019年からOCI技術者の育成と、OCI/Oracle データベース両方の技術支援のサービスを開発してきました。
特に、クラウド移行のプロジェクトは、短期間でシステムリリースしたいお客さまが多い傾向です。そういったお客さまのために、OCI/Oracle データベースを事前にテンプレート化し、開発スピード/開発効率を向上させるべく、ソリューションの開発に取り組んできました。
Oracle データベースで培ってきたデータベースのノウハウに加え、OCIではネットワークやセキュリティなど幅広く設計し、テンプレート化をしました。当時新入社員だった私はOCIのソリューション開発を通して成長させていただきました。
最近では、OCIの引き合いも多くいただき、自分たちのソリューションでお客さまのシステムを実現することにやりがいを感じています。
三澤様:
また、マルチクラウドの需要が伸びている昨今、2023年から日本オラクル社と共同でマルチクラウド構成(Interconnect、ODSA)を検証し、基幹システム向けのOCI-Azure構成を想定した業務特性別の性能影響を明らかにしました。これにより、マルチクラウド移行の実現性のアセスメントサービスを確立し、本事例でも活用することができました。
▼OCIとOracle データベース両方の技術を兼ね備えたエンジニアを育成する中で、苦労された点や工夫された点を教えてください。
我々のチームの中でいうと、もともとOracle データベースの知識を備えたエンジニアが多くいる状況で、パブリッククラウドの知識は足りなかったので、ネットワークやサーバーの知識を新たに学ぶ必要がありました。OCIでどのような開発をしていけるかと考えたときに、まずは開発する際のパラメータを調べ、どうすればデプロイできるかなどを一から皆で触ってみる、というところから始めました。そのため、一緒に携わったパートナー様も含め、現場では開発後には全員OCIの基本的なスキルセットを獲得し、知識が蓄積されるというところまで持っていくことができたのがとても良かったと思っています。
パートナー様の方も当時OCIは初めてで、まだ引き合いもない状態だったのですが、とにかくOCIを触ってテンプレートをまず構築してみていたおかげで、チームでは引き合いが来る前にだいたいのOCIの理解ができていました。日本オラクル社のCoEチームにもご助力いただき、迅速な立ち上げができたと思います。
パブリッククラウドの知識取得については、グループ会社で先行して他のパブリッククラウドを手がけてきたメンバーがチームに参加し、OSやハードウェアなどに関して技術者同士の連携や技術補完ができていました。
クラウド固有の部分を理解しなければならず、クラウド固有の機能がオンプレミスではどれに相当するかを一から調べていくなど、知識の少ない技術の底上げには当時苦労しましたが、それぞれのチームから集まってきたクラウド経験者の連携や、日本オラクル社のCoEチームからの情報提供を活用しました。
▼テンプレートの構築についてくわしくお聞かせください。
テンプレート構築のための勉強会から開発までだいたい6か月くらいの期間で完了させました。
チームのメンバーはメインで携わったのが6人から7人ぐらい、トータル10人程度です。半年程度で作ったあとは、アップデートや仕様変更に合わせ、随時メンテナンスをして最新化しています。
一からクラウド向けにテンプレートを作成するにあたって、参考書などもない状況からのスタートでした。地道にマニュアルなどを見て勉強、日本オラクル社のセミナーにも参加し、オンプレミスとクラウドでの考え方の違いや新たな考え方なども把握/理解をした上で着手しました。考え方の違いをしっかり学んでから、というのがとても大切だと思います。
▼今回のみずほリース様のプロジェクトの概要について教えてください。
みずほリース様が新たな金融サービス・事業に取り組む中で、データを一元的に集約し横断的に分析できるデータ活用基盤を構築したいという要望がありました。現在オンプレミスにある基幹システムから、OCI上に分析基盤を新たに導入するプロジェクトです。
具体的には、データ連携の方式設計から、データベースを含むOCIインフラ構築、データ移行を3か月という短期間で対応しました。
▼今回のプロジェクトに取り組むにあたり、チームとしてどのような準備をしていましたか。
片山様:
プロジェクトリーダーとして、OCIとOracle データベースの技術支援的まとめに携わりました。
今回のみずほリース様の事例の特徴として、既存の本番環境で動いているシステムがある中でOCIに分析基盤を新たに作る、というものがありました。現行のシステムが稼働中のため、そちらに影響がでないように、かつ高速なデータ同期ができること、というポイントに加え、準備期間が非常に限られており、3か月という短期間でデータ同期を完了させるという技術的な課題もありました。
既存システムに影響なく、という点は、我々日立製作所のOracle データベースとOCI両方に詳しいナレッジがありますので、そこを活用して、お客さまの要求を満たすような方式で、既存システムが稼働しながら問題なくタイムリーな同期ができたと思います。
準備期間が3か月と短い、という点については、我々はOCIをスムーズに立ち上げるためにスターターパックというものを準備しておりますのでこちらを活用しました。お客さまに最小限のヒアリングシートに記入していただくだけで、それに応じた環境をデプロイできるような仕組みとなっています。
▼今回のプロジェクトで工夫された点や苦労された点についてお聞かせください。
分析基盤のデータベースの構築にあたって、「データ活用基盤の構築と同時に、既存システムの性能へ影響が出ないようにすること」「迅速な立ち上げとスモールスタート」というニーズがありました。
工夫した点の1点目は、既存システムに影響を与えずにデータを同期する方法(Oracle Data Pump、 Oracle GoldenGate、Oracle Recovery Manager)を、お客さまニーズと現行運用を照らし合わせ比較・検討したことです。
2点目は、迅速な立ち上げに向け、OCIへのデータベース移行ノウハウ(セキュリティ対策を含む)をテンプレート化したスターターパックを使用し、3か月でデータ活用基盤を構築したことです。
▼マルチクラウド対応に関して苦労した点はありますか。
マルチクラウドについては、OCI以外のクラウドに触れるのが初めてということで、一から学び直しの苦労がありましたが、社内で問い合わせできる相手の協力を得て操作を覚えていきながら環境構築を進めて、うまく結果を出すことができたと思います。
こういった苦労のおかげで、お客さまからの突発的な相談にも、実際の苦労話も交えながら提案ができるというよい結果につながり、お客さまの満足の獲得に貢献することができました。
OCIを今後学ぶ技術者へのアドバイスとしては、我々はほぼゼロの状態から学びましたが、他のパブリッククラウドを学んでいれば、敷居はそれほど高くはないと思います。一歩踏み込むのに心理的な障壁があるかもしれませんが、そこはぜひ恐れずにチャレンジしてみていただきたいです。当社では他のパブリッククラウドやOCIの違いを社内的な教育として勉強会のような形で今期展開していく予定です。
OCIと他のパブリッククラウドとの間に決定的な違いというと、クラウドリソースの管理単位であるコンパートメントやセキュリティの点でしょうか。セキュリティではカギをかけたり開けたりの考え方が異なります。その他の点では、他のパブリッククラウドとはわりと一緒の部分も多いかもしれないですね。困ることはあまりないです。
当社でもOCIのプロジェクトはだんだん増えていており、勉強会などを通じてOCIができるエンジニアを増やしていく取り組みを始めるところです。一から学ぶためには心理的障壁があるかもしれませんが、一歩目を踏み出して触ってみてもらえれば、そこまで技術的な難易度は高くないと思っています。ぜひチャレンジしてほしいですね。
▼3か月という短期間で全社規模のデータ活用基盤を構築するプロジェクトを実現させた、日立製作所の強みとはどんなところだと思われますか。
既存システムに一切影響を出さずに円滑にプロジェクトを推進するために、チームがこれまで数多く携わってきたミッションクリティカルな案件での実績や、チーム内に蓄積されている膨大な量の評価/検証をもとに、プラットフォームの違いやデータベースのバージョンなどへの対応や、これくらいのデータ量ならこれくらいの時間が必要、と判断できるリアルな情報やノウハウなど、我々の過去の経験値がお客さまから高く評価されたと考えています。
ミッションクリティカルな移行を経験しているメンバーも多いので、発生しがちな問題も過去に経験済みということもあり、ハマりそうなところを前もって潰しておくことができるのも強みだと思っています。
▼プロジェクト完了にあたり、お客さまからどのような声をいただいたか教えてください。
都度発生する細かい悩みや相談にも親身に寄り添ってもらい、譲れない要件を満たして実現可能な手法をいつも提案してくれたと、おっしゃっていただけました。
▼「2024 Oracle Partner Awards」のグローバルで最も優れたパートナーを表彰する「Regional Best in Class Award in Customer Success」受賞に際して、一言いただければと思います。
今回Globalからここまで大きな賞をいただけたことを本当に喜んでいます。受賞のニュースリリースを出したので、社内からも声をかけられたり、相談があったりと引き合いにもつながってきていると思います。
▼ご自身がこれまでに取得した、もしくは今後取得予定のOracle認定資格を教えてください。
片山様:
■取得済み
・Oracle Autonomous Database Cloud 2023 Certified Professional
・Oracle Cloud Database Migration and Integration 2021 Certified Specialist
・Oracle Cloud Infrastructure 2021 Certified Architect Associate
・Oracle Master Platinum 9i
■今後
・Oracle Cloud Infrastructure 2024 Certified Architect Professional
三澤様:
■取得済み
・ORACLE MASTER Gold DBA 2019
・Oracle Cloud Infrastructure 2023 Certified Architect Associate
■今後
・Oracle Cloud Infrastructure 2024 Certified Architect Professional
野中様:
■取得済み
・ORACLE MASTER Gold DBA 2019
・Oracle Autonomous Database Cloud 2023 Certified Professional
・Oracle Cloud Infrastructure 2023 Certified Architect Associate
・Oracle Cloud Infrastructure 2024 Certified AI Foundations Associate
■今後
・Oracle Cloud Infrastructure 2024 Certified Architect Professional
▼チームとしてOracle認定資格取得に関して目標はありますか?
技術はどんどん進化するので、最新バージョンの資格をアップデートして取得、クラウドもProfessionalも取得していきましょうという目標を立てています。主管部が提案の際に技術者がいることをアピールできるように、という狙いがあります。
上位資格に関しては集まって勉強会を開催したり、若手に先輩がアドバイスしたりするなど、チーム内で資格が取得しやすい環境を整えています。
▼リモートワークなどの働き方に関して、チームとして工夫されている点を教えてください。
リモートならではの工夫としては、我々Oracleテクニカルチームはほぼリモートで対応していますが、お客さまの声を聞き取ったり中身に触ったりするフロントのSE側は訪問するなど、社内でうまく棲み分けしながらお客さまをサポートしてきました。みずほリース様の場合は、社内のルールにのっとり、ある程度セキュリティが担保されていればリモートでもシステムにアクセスできると伺っていましたので、その点では会議も含めリモートでの苦労はありませんでした。
私たちのチームでは現在リモートが主ですが、お客さまの業種に依存するところが多々あり、お客さまに合わせて対応しています。用途別にリモートとオンサイトを組み合わせていくという指針のもと、自宅でも集中して技術検証や勉強をできる環境を会社が支援しています。オンサイトでのディスカッションとリモートでのクイックな打ち合わせを活用し、オンサイトも積極的に利用しながら、集中したい場合には自宅で、という形です。リモートでも情報共有しやすいよう、社員にはチーム内の情報共有インフラとしてツールが提供されています。
オフィスでは、全員分の個人席から、部署をまたいでどこに座ってもいいシェア席(フリーアドレス)に変更され、簡単な打ち合わせやディスカッション、雑談がしやすいよう、ソファの置かれたスペースも増えています。
また我々のチームでは、週に2日出社して直接会う機会をつくり、お互いの仕事を共有することで、誰かが課題を抱え込んでいないか確認できるようになっています。
▼今後どんな人たちとチームで一緒にやっていきたいと思いますか。
クラウドのプロジェクトがとても増えて全体の過半数を超えているので、ぜひクラウドのスキルのある方と一緒に働きたいです。また、自分がリーダーだと思って取り組んでくれる人や、クラウドを知らないお客さまにもきちんと提案できる、またはそうありたい人を大募集です。
複数のパブリッククラウドを見られる人も歓迎です。我々自身、新しい技術に速いスピードで取り組むよう努めているので、何かが世の中に発表されてすぐ触って取り入れてお客さまに正しく提案できることを楽しんでくれる人がいいですね。
社会に役立つシステムに、安全安心な品質とスピードのバランスをうまく取りながら、最新の技術に関心を持って取り組む、ということが我々のモットーなので、従来の安定した信頼性の高い技術ではなく新しい技術の活用について、若手エンジニアをリーダーとしてプレリリース段階から検証を始めていっています。そのようなことに面白さを見出してくれる人と一緒に仕事できたらうれしいです。
昨年からエンジニアのプロフェッショナル人材のキャリアパスを整備し新たに求人が始まっていますので、ぜひ検討していただければと思います。
▼今後のキャリアプランをお教えください。
片山様:
最近、OCIの引き合いをいただくことが増えました。テクニカルサービスのメンバー以外にも、フロントのSEを含めたOCI人材の育成を進めていきたいです。
三澤様:
上記のマルチクラウド検証に加え、現在は Autonomous Database の機能を活用した基幹システムの運用コスト削減に向けた検証を実施しています。お客さまに最適なインフラを提供できるよう、今後も最新技術を検証し、サービス化を推進します。
野中様:
2024年から急ピッチで生成AI関連の検証やイベントが増えました。
業務データの活用の幅が広がり、お客さまの期待も大きいので、その期待にお応えできるエンジニアをめざします。
▼同じエンジニアの皆さまへメッセージをお願いいたします。
片山様:
クラウド技術の急速な進化についていくため、積極的にOCI環境に触れ、社内外にアウトプットする機会を増やしていきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。
三澤様:
OCIのアップデートに合わせて、マルチクラウドや自律型データベースを検証することにより、お客さまに新たな価値を提供できるようになりました。皆さんも最新の技術を積んでクラウド事業を盛り上げていきましょう。
野中様:
Oracle Database 23aiではAI Vector Searchがリリースされ、生成AIのRAG用途Oracleデータベースが利用できるようになりました。
私も、実際に生成AIとOracle Database 23aiを連携した検証を対応(日立、日本オラクルと生成AIを活用した協創プロジェクトを実施 – Digital Highlights:デジタル:日立)し、Oracle データベースの活用場面が大きく広がる期待感を持っています。
Oracleにかかわるエンジニアの皆様と協力し、お客さまの業務データ活用を一緒に考えて、実現するお手伝いができればと思っています。
【OPN編集後記】
今回は、日立製作所様から、OCIとデータベース両方の高いスキルを磨きながら、お客さまの要望に寄り添うエンジニア、片山様、三澤様、野中様にスポットライトを当てお伺いしました。
このように、日立製作所様が今まで培ってきたデータベースでの実績に加え、OCIやマルチクラウドへの対応にもスピード感を持って臨むことで、ミッションクリティカル領域のお客さまからも高い満足度を勝ち得ている強みを理解することができました。
お三方の今後ますますのご活躍をお祈りしております!