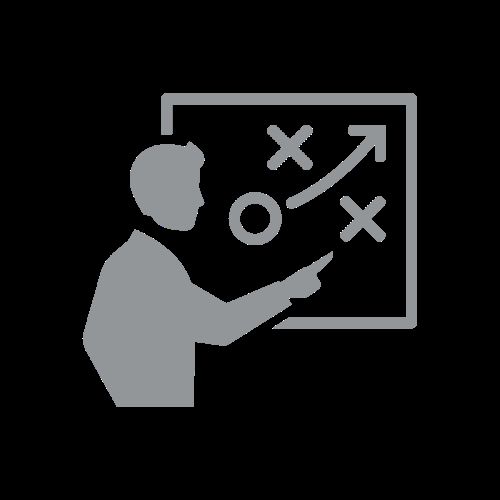2月末にORACLE MASTER Gold DBA Week と題して、ORACLE MASTER Gold DBA 2019の主要出題分野であるマルチテナント・アーキテクチャとバックアップ・リカバリについて次の無償セミナーを開催します。
2025年2月26日(水) 15:00〜17:00
【オンライン限定】ORACLE MASTER Gold DBA Week Oracle University 人気講師が解説する マルチテナント・アーキテクチャ
2025年2月27日(木) 15:00〜17:00
【オンライン限定】ORACLE MASTER Gold DBA Week Oracle University 人気講師が解説する バックアップ・リカバリ
Oracle Universityの人気講師が実機デモも交えて分かりやすく解説します。
さて、この記事では、ORACLE MASTER Gold DBA 2019 のバックアップ・リカバリ分野からの出題トピックごとの概要を簡単にご紹介するとともに、何故バックアップ・リカバリを学習する必要があるのかをお話ししたいと思います。
マルチテナント・アーキテクチャの知識の必要性についての記事はこちら
RMANの設定および使用
RMANのCONFIGUREコマンドを使用すると、バックアップの保存ポリシーやバックアップのデフォルトの格納先、バックアップの暗号化や圧縮などの永続設定を行うことができます。どのような設定項目があるのか、知っておくことは重要です。
RMANでバックアップなどを行った記録などRMANメタデータをRMANリポジトリと呼びます。RMANリポジトリは制御ファイルに保持されますが、リカバリ・カタログという別のデータベースに格納することもできます。リカバリ・カタログを使用すると、制御ファイル破損時のリストア、リカバリが容易になります。
バックアップの方法および用語
バックアップ・セットなのか、イメージ・コピーなのか、完全バックアップなのか、増分バックアップなのか、バックアップ方法によってバックアップの所要時間も、サイズも、リカバリの所用時間も変わってきます。Oracle推奨のバックアップで使用される増分更新バックアップでは、増分バックアップを使用してイメージ・コピーをロールフォワードしておくことで、結果的にリカバリ時間を短縮できます。また、非常に大規模なファイルをバックアップする場合、マルチセクション・バックアップを使用するとパフォーマンスが向上する可能性があります。ケースバイケースで最適なバックアップ方法が異なるので、それぞれの特徴を知っておくことは重要です。
障害の診断
データ・リカバリ・アドバイザを使用すると、シンプルなコマンドながら、障害発生時に検出、分析および修復のアドバイスを得ることができます。障害発生時は冷静さを失いがちですので、データ・リカバリ・アドバイザは有用です。
リストアとリカバリの概念
メディア障害発生時は、バックアップをリストアし、リカバリを行います。リストアの時間が取れない場合は、イメージ・コピーへの高速切り替えという選択肢もあります。完全リカバリは最後のコミットまで復旧するリカバリです。一方、ポイント・イン・タイム・リカバリは不完全リカバリとも呼ばれますが、なんらかの事情でデータベースをある過去の時点の状態に戻すリカバリです。特定の表領域だけを過去の時点に戻す表領域ポイント・イン・タイム・リカバリもあります。
リカバリの実行
データファイル破損時の、RMANによるリストア、リカバリに加えて、ブロック破損時にはブロック・メディア・リカバリという、破損ブロックだけをピンポイントで修復する方法もあります。REDOログ・ファイルが破損した場合は、REDOログ・グループのステータスや破損の状況に応じて、取るべき対応が変わってきます。パスワード認証ファイルが破損した場合は再作成です。あらゆる障害シナリオに対して、リカバリ手順を明確にドキュメント化しておくことは非常に重要です。
フラッシュバック・テクノロジの使用
フラッシュバック問合せ、フラッシュバック・バージョン問合せ、フラッシュバック表、フラッシュバック・トランザクション問合せなどはUNDOのデータを使用して、ほんの少し過去の表のデータを見たりする機能です。フラッシュバック・データ・アーカイブは、指定した長期間にわたって表単位で変更履歴を保持する機能ですが、データの改竄を抑止できるので、コンプライアンスや監査といった用途で使用できます。
また、フラッシュバック・データベースは、フラッシュバック・ログという追加のログを使用し、データベースを過去の指定の時点に戻せる機能です。ポイント・イン・タイム・リカバリとは、過去に戻す仕組みが全く異なるので、それぞれメリット・デメリットがあります。
データの転送
古くからあるデータの移行方法は、ダンプファイルにエクスポートし、それを移行先でインポートするという手段です。しかし、データ量が多い場合は、時間がかかります。そこで出てきたのが、表領域の転送(トランスポート)という手法で、データ自体をエクスポートすることなく、表領域セットのデータ・ファイルを転送するという方法です。正確にはメタデータはエクスポート・インポートする必要がありますが、こちらは表領域そのもののエクスポート・インポートに比べて短時間で行えるので、転送の方が高速です。その機能の発展形で、RMANを使用することでエンディアンの異なるプラットフォーム間での表領域の転送も行うことができます。また、異なるプラットフォーム間(ただしエンディアンは同じ)でのデータベース全体の転送も可能です。データベースを再作成して、Data Pumpエクスポート・インポートで移行するか、はたまたRMANを使ってデータベースを転送するか、選択肢が増えています。
データベースの複製
バックアップ手順やリカバリ手順のテストやアップグレードのテストといった用途でデータベースの複製を作りたいことがあります。RMANを使用すると、ソースデータベースのバックアップから複製したり、アクティブなデータベースから複製したり、状況に応じて柔軟にデータベースを複製することができます。(参考:第10回:RMANを用いたデータベースの複製)
RMANのトラブルシューティングおよびチューニング
バックアップに要する時間を改善したい時、何から着手しますか。まずは、ボトルネックが読み取りフェーズにあるのか、それとも書き込みフェーズにあるのかを判別し、状況と構成に応じたチューニングを行なっていきます。
さて、ORACLE MASTER Gold DBA 2019のバックアップ・リカバリ分野の出題トピックについて、簡単にご紹介してきましたが、バックアップ・リカバリを勉強していると、初めのCONFIGUREコマンドから大量に覚える項目が出てきて、難しいと感じるかも知れません。どういうケースで使うのだろうか、自分が関連しているシステムではどのような設定になっているのだろうか、こういったことを考えながら一つ一つ見ていくと少し面白くなってくるのではないでしょうか。
データベース管理者は、データベースのバックアップ、データベースの複製、データベースの転送など、行うべきタスクが沢山ありますが、それぞれにおいて様々な方法、選択肢があります。多くの選択肢の中から、その環境での最適な選択肢を選べるようになる、それがバックアップを学ぶ理由です。知っている選択肢が多ければ多いだけ、最適な選択肢を自信を持って選べます。
また、データベース管理者は、ディスク・クラッシュからの復旧、想定外の人為ミスからのデータの復旧、突然として発生したあらゆる障害に対して、冷静に原因を切り分け、ダウンタイムが最短となる方法でリカバリしなければなりません。リカバリ時の判断ミスや操作ミスは、更に悲惨な状態を引き起こします。そんなことが起きないように、あらゆる事態を想定してリカバリ・テストを行い、リカバリ手順書を用意しておく必要があります。これがリカバリを学ぶ理由です。
ぜひ、2025年2月27日(木)開催の
【オンライン限定】ORACLE MASTER Gold DBA Week Oracle University 人気講師が解説する バックアップ・リカバリ
セミナーに参加して、バックアップ・リカバリを学習する取り掛かりにしていただければと思います。
参考リンク